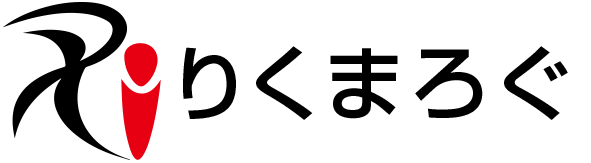北九州市小倉北区の中心部を流れる紫川(むらさきがわ)には、合計10個の個性的な橋が架かっており、それら10個の橋を総称して「紫川十橋」と呼びます。
今回は紫川十橋のひとつ、室町大橋(愛称は「火の橋」)について写真と共に詳しく解説します。
なお、紫川十橋のすべてをまとめたページも作成しています。紫川十橋が誕生した由来や各橋の解説などを掲載していますので、よろしければそちらもご覧ください。
-

-
紫川十橋:北九州市小倉北区、紫川に架かる10個の個性的な橋
北九州市小倉北区の中央を流れる紫川には10個の個性的な橋が架けられており「紫川十橋」と呼ばれています。10個すべての橋を徒歩で巡り撮影してきた写真と共に、各橋の周辺にある観光スポット情報も交えて紹介します。
室町大橋は、北から数えて2番目にある橋

「火の橋」という愛称を持つ室町大橋は、紫川十橋の中では北から数えて2番目の位置にあります。

国道199号線の「紫川大橋東」交差点から南方向に曲がり、紫川さくら通りを川に沿って直進。
山陽新幹線やJR鹿児島本線などの高架下を通過し、そのまま南へ進むと室町大橋が見えてきます。
紫川十橋の中では最北端に位置する紫川大橋(海の橋)からだと、5分前後ほど歩けば着きます。

室町大橋は平成3年(1991年)4月に完成しました。
歩道に設定されている高欄は、波の模様をイメージして作られているのだそうです。
炎のオブジェには実際に火が点火される

室町大橋は片道1車線の車道と、両側に歩道があります。
両方の歩道には、紫川に突き出るような形で炎のオブジェが合計8個、一定間隔で設置されています。

紫川では明治時代まで鵜飼いがおこなわれていたのだそうです。
鵜飼いとは、鵜(う)という鳥に魚を獲らせる伝統的な漁法。岐阜県・長良川の鵜飼いが有名です。
室町大橋の歩道に設置された炎のオブジェは、鵜飼いの際に魚を誘い寄せるために使う漁り火(いさりび)をモチーフとしてデザインされたそうです。
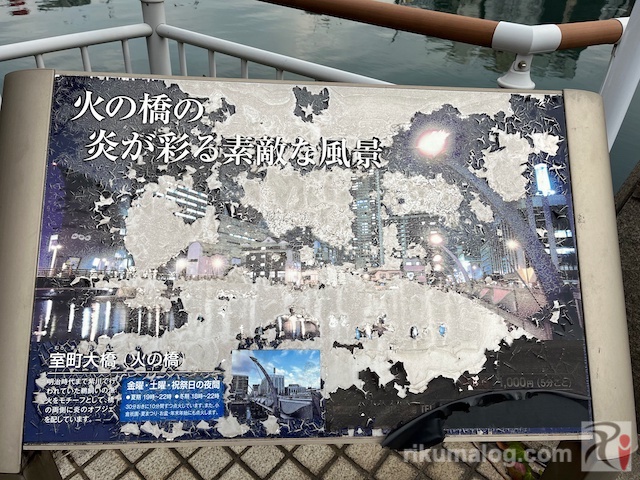
東西の端には室町大橋の案内板が設置されているのですが、どちらも時間の経過と共に風化してしまい、ボロボロになっていました。
おそらく夜間にライトアップされた室町大橋の写真が紹介されているのだと思うのですが、判別不能な状態となっています。
案内板の左下にある判読可能な解説によれば、炎のオブジェには実際に火が点火されるそうです。
- 金・土・祝祭日の夜間
- 夏季は19時〜22時
- 冬季は18時〜22時
上記の期間、30分おきに10分間ずつ点火されているそうです。
「小倉祇園・夏祭り・お盆・年末年始の期間中も点火されている」とも書かれていました。
また、上記の期間以外でも、申し込みをすることで点火は可能なのだそうです。
室町大橋の横にある市営室町駐車場で申し込めば、お好きな時間に点火してもらえるそうです。ただし有料です(10分間で2,000円)。
友人や恋人、奥さん・旦那さんや家族の皆さんを室町大橋に連れてきて、サプライズで炎のオブジェを点火させると大変喜ばれるのだそうです。素晴らしいですね。
室町大橋、周辺の風景
室町大橋・東側の風景

室町大橋の東側にある「室町大橋東」交差点はT字路になっており、直進はできません。
このあたりは歓楽街になっていて、ホテルや夜のお店がいくつか点在しています。
写真中央の少し右側に見えている、最上部が円形になっている大きなビルは、JR小倉駅前に建つ商業施設、セントシティ。
最初は小倉そごうとして建設されました。そごうの経営破綻後は名称や経営母体が変遷し、2021年4月から現在のセントシティとなっています。
室町大橋・西側の風景

西側に伸びる道路をそのまま直進すると、JR西小倉駅に着きます。室町大橋からは500メートルほど。徒歩でも5分少々の距離。
室町大橋と西小倉駅のちょうど中間あたりにはヤマダ電機の小倉本店があります。
室町大橋・北側の風景

北側にはJR日田彦山線やJR鹿児島本線の鉄橋が手前にあり、その奥で一段高くなっているのが山陽新幹線の鉄橋です。
JRや新幹線の向こう側には紫川大橋(海の橋)があります。しかし上の写真では見えていません。
室町大橋・南側の風景

南側には、まず右側に巨大商業施設、リバーウォーク北九州がそびえ立っています。
写真中央には、紫川十橋で北から数えて3番目にあたる「常磐橋(木の橋)」がすぐ近くに見えています。